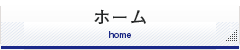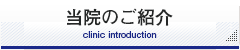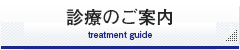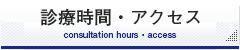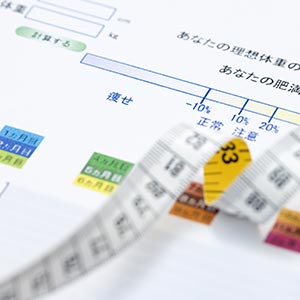風邪、咽頭炎、扁桃腺炎、気管支炎、肺炎などの急性の感染症から気管支喘息、慢性閉塞性 肺疾患(肺気腫)、慢性気管支炎、肺結核後遺症、肺非結核性抗酸菌症、気管支拡張症などの慢性の呼吸器疾患まで、呼吸器(肺、気管)に関することなら何でもご相談下さい。
咳が治りにくい、痰が切れにくい、動くと息切れがするといった症状のある方は、呼吸器の病気が隠れている可能性もありますので、お早めにご来院下さい。
長い間、咳が続いていることはありませんか?
風邪にしては咳がなかなかおさまらない、不思議だと思って、そのままにしていることはありませんか?そのような場合には漫然と咳止めの薬を飲んでいるだけでは、症状が治まらないことが多く認められます。
咳の症状を認める場合には、その咳をもたらす病気がどんなものであるか(背後にある病気がどんなものであるか)を明らかにして対処していくことが大事になります。
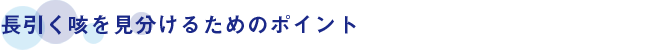
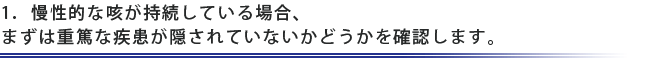
このときには胸部レントゲン写真を撮影します。胸部レントゲンで異常を認める疾患としては肺癌、肺結核、肺炎、胸膜炎、気胸などがあります。まずは、胸部レントゲンでこれらの疾患がないかどうかを確認します。
![]()
「胃食道逆流症」「高血圧治療薬(ACE阻害薬)の内服」「副鼻腔炎による後鼻漏」が原因としてあげられますので、これらの要因がないかどうかを診ます。
胃食道逆流症:胃酸が食道に逆流することによって起こります。症状としては胸焼けを伴います。食後に咳が悪化する、体重が増えると咳が増加するという特徴があります。
高血圧治療薬としてのACE阻害薬の内服:高血圧の治療薬としてACE阻害薬を内服している場合に痰を伴わない咳を認めることがあります。この場合にはACE阻害薬の内服を中止すると咳嗽は改善します。
副鼻腔炎(蓄膿症):膿性痰、後鼻漏(鼻の奥の方にいつも鼻水が流れている感じを自覚すること)、副鼻腔の痛みを自覚することがあります。
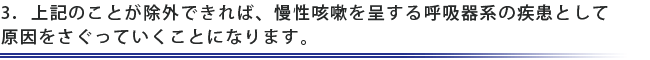
一般的には「気管支喘息」「慢性気管支炎」「かぜ症候群後の咳嗽」「副鼻腔気管支症候群」「咳喘息」「アトピー咳嗽」「その他の原因」に分類されます。
慢性気管支炎:現在喫煙をしていて痰を伴う咳を認める場合には慢性気管支炎を疑います。禁煙によって症状は改善します。
かぜ症候群後の咳嗽:咳が2~3週間続いているという患者様では、「かぜ症候群」が原因となっている場合が最も多いケースです。
この場合、咳とともに発熱、咽頭痛、痰、関節痛、頭痛などの感冒症状を認めているかどうかが大事な所見になります。通常は4週間以内に自然軽快傾向がみられるので、この点が診断のポイントになります
副鼻腔気管支症候群:呼吸困難を伴わない咳嗽(しばしば湿性)を認めます。後鼻漏、鼻汁および咳払いといった副鼻腔炎症状を認めます。マクロライド系抗菌薬や去痰剤が有効です。
咳喘息:気道の過敏性(色々な刺激に対する反応性)が亢進し咳を認めるようになります。気管支喘息のようにヒューヒューぜいぜいといった息苦しさを自覚することはありませんが、慢性的に咳を認めます。気管支喘息の亜型あるいは前段階と位置づけられ、場合によっては気管支喘息に移行する方もいらっしゃいますので注意が必要です。
アトピー咳嗽:アトピー素因に関連し、気管支拡張薬がまったく無効な慢性乾性咳嗽を特徴としています。気管支喘息への移行は認められません。
とにかく、以下ような症状がおありの場合には、お早めにご来院されることをお勧め致します
・咳やたんが続いている。
・風邪をひくと咳が長引く。
・咳止めを飲んでも、咳が止まらない。
・明け方になると、咳のために目が覚めます。
・咳、息をするときに「ゼーゼー、ヒューヒュー」と音がする。
・こどもの頃に「喘息」ではないかと言われた。
・親、兄弟に「喘息」の方がいる。
![]()

睡眠時無呼吸症候群とは、読んで字のごとく「睡眠時」に「無呼吸」状態になる病気です。
英語ではSleep Apnea Syndrome(SAS)と書きます。「無呼吸」とは、10秒以上の呼吸停止と定義され、この無呼吸が1時間に5回以上または7時間の睡眠中に30回以上ある方は睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
無呼吸が続くことで体に負荷が掛かり、生活習慣病(高血圧や心疾患など)になることや、昼間の眠気による事故(交通事故、労災事故)に関係するため、ご本人だけでなく社会的にも問題となってしまいます。
睡眠中の無呼吸を指摘された場合、または自覚症状がある場合などは、なるべく早めに受診されることをお勧めします。
睡眠中のことはご自身では分からない場合も多いので、可能であればご家族やパートナーと一緒に受診されると良いでしょう。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)の治療法
睡眠時無呼吸症候群の治療には、「生活習慣改善」と「内科的治療」「外科的治療」「歯科装具」などがあります。睡眠時無呼吸症候群では肥満による上部気道への過剰な脂肪沈着とも関連があるため、生活習慣の改善が欠かせません。
![]()
生活習慣病の治療と同様に、運動療法やアルコールの制限などを行います。
減量:肥満は首周りにも脂肪が沈着しているため、気道を閉塞させます。食事療法、運動療法を実施し減量を試みます。減量することにより無呼吸が少なくなったり無くなる方もいます。減量が成功した方は、気を緩めず維持するようにしましょう。
アルコール制限:アルコールの摂取は、気道の筋力を低下させる作用があるためよくありません。就寝前の飲酒はやめましょう。
禁煙:アルコール同様、血液中の酸素の濃度を低下させたり、咽喉頭部の炎症を起こすことがあり、悪影響があります。できるだけ禁煙をしましょう。